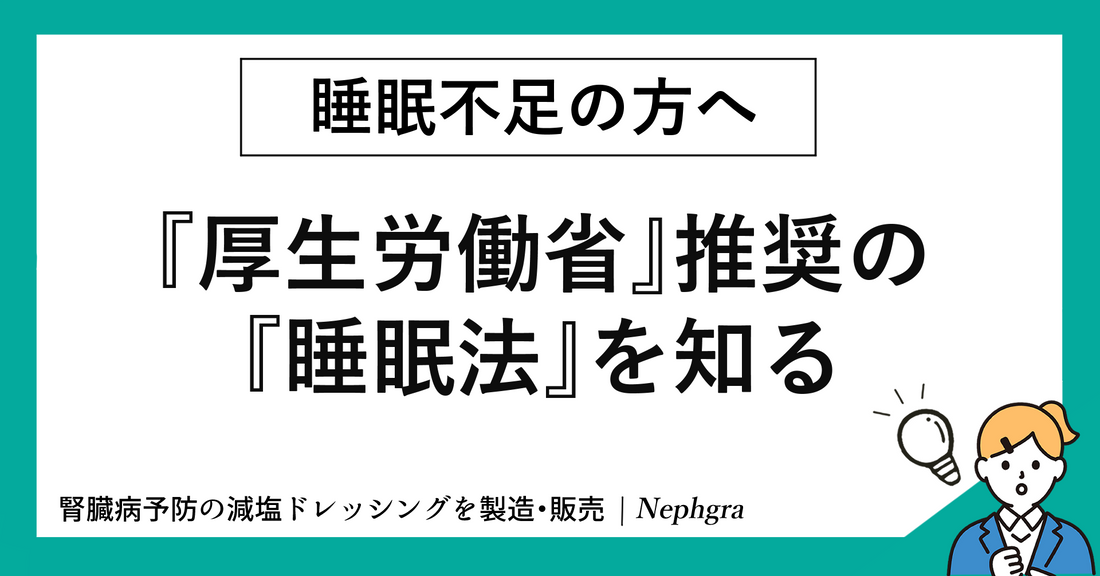
睡眠不足の方へ。『厚生労働省』が推奨する睡眠方法を知る
こんにちは。減塩ドレッシングの製造・販売をしているNephgraです。
人生の約3分の1を占めるといわれる睡眠。人によっては、つい後回しにしがちではないでしょうか。直ぐ目に見える異変が発生することはないですし、どうしても睡眠を削らなければいけない状況はあります。
ただ、睡眠による影響を短絡的に考えてしまうと生涯に渡って大きな負債を背負う可能性があり、今は良くても10年後の自分が振り返って、後悔する行動を積極的に取ってしまっている、なんてことにもなり兼ねません。
今回は、厚生労働省が2024年11月版で発行の「良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと」を参考に紹介させて頂きます。(URLは末尾に記載。ご興味のある方は是非一読ください)
「睡眠不足」「寝だめ」が引き起こす悪影響が無視できない程に多い

一時的な睡眠不足ではなく、数日にわたって睡眠不足が続いている状態を「睡眠負債」と呼びます。この状況に陥っている人は少なくありません。
それを解消するため、休日に長く眠る「寝だめ」を行う人は多いのではないでしょうか。意識してなくても、休日の睡眠時間が平日より長くなってしまうことがあるはずです。この就寝/起床時間のズレを「ソーシャルジェットラグ」と呼ばれ、体内時計が乱れるという代償が伴います。
「ソーシャルジェットラグ」は健康への悪影響を与えます。「肥満」「糖尿病」などの生活習慣病・「脳血管障害」や「心血管疾患・うつ病」の発症リスクとなることが報告されています。また日中の眠気や疲労に加え、注意力や判断力の低下、学業成績の低下にも影響します。
徐々に身体を蝕む睡眠不足ですが、数値化されて毎日目視できるものではありません。多くは病気を発症してから原因の一つだと知るために後回しにしてしまうのも仕方がないといえます。
不眠について
「なかなか寝付けない」「寝ていても途中で目が覚めてしまう」などの不眠の症状は、日本人の「15~25%」の人が経験する誰にでも起こりうる症状です。多くは感情的な出来事をきっかけとした心理的なストレスと関連して起こる一時的なものです。
ただ眠れないことを過剰に心配するあまり、眠るために頑張りすぎることもあります。その場合、睡眠の習慣が不適切になってしまい不眠の症状が長引く場合もあるのです。不眠症状の4つのタイプをご紹介します。
1.入眠障害:横になっても中々寝付けない。悩み事が多いと生じやすい
2.中途覚醒:睡眠中に何度も目が覚める。 一度目が覚めると中々寝付けない
3.早朝覚醒:予定よりも早く目が覚めてしまい、そのあと寝付けない
4.睡眠休養感の低下:睡眠時間は十分にもかかわらず、睡眠で休まった感覚がない
不眠の背景にはうつ病や不安症といった精神疾患の他、閉塞性睡眠時無呼吸や身体疾患が隠れている場合もあります。可能なら医療機関への相談を検討ください。
良い睡眠のための工夫
1.寝室の環境を整える
光:朝日を浴び、日中は明るく、夜は暗い環境を心がけることで体内時計が整いやすくなります。
湿度:室内は暑すぎず寒すぎない温度を心がけましょう。就寝1~2時間前にお風呂に入り一度体温を上げることで眠りにつきやすくなります。
音:騒音は寝つきを悪くしたり、睡眠の維持を困難にする可能性があります。できるだけ静かな環境で眠りましょう。
2.日中の運動・身体活動を増やす
運動:日中に体を動かし、適度な疲労を感じることで寝つきが促され、中途覚醒が減り、睡眠の質が高まります。習慣的に運動している人の70%以上は睡眠の質が良いことが分かっています。
世代:働く世代は中・高強度の身体活動、リタイア世代は低強度の身体活動がリスクを減らします。就寝2~4時間の運動はかえって目を覚ますので避けましょう
食事:朝食を抜かず、寝る直前の食事は控えましょう。朝食を抜くと体内時計は後ろにずれてしまい、寝付きが悪く睡眠不足になりやすくなります。
3.嗜好品とのつきあい方を見直す
カフェイン:過料な摂取は控えましょう。1日のカフェイン摂取量が過量な場合は午前中の摂取であっても夜の睡眠に影響することがあるため注意が必要です。
お酒:晩酌は控えめに寝酒はやめましょう。習慣的な寝酒は、睡眠の質を悪化させるだけでなく、長期的には健康を害する可能性があります。
喫煙:タバコに含まれるニコチンには覚醒作用があり、眠りを妨げます。喫煙歴の長い人では閉塞性睡眠時無呼吸のリスクが高くなることにも注意 が必要です。
POINT:眠れない時は?
感情が高ぶった状態のまま眠ることはできません。眠りに適した状態にするために、自分に合ったリラックス法を持つことが大切です。リラックス法を使っても寝付きが悪く20分以上眠れない場合は…
①一度寝床を出て
②暗い場所でリラックスして過ごし
③無理に寝ようとせず、眠気を感じたら寝床に戻りましょう。
筆者個人は寝床で"寝ようとする"より"力を抜いた状態を維持しよう"と考えるようにしていて、一定の効果を感じています。
まとめ
今回は厚生労働省が推奨する睡眠方法についてご紹介しましたが、眠るための対処法は調べれば多くの知見が見つかります。しかし、難しいもので睡眠のことを考えれば考えるほど実際の就寝時にリラックスできなくなり、また眠れない日を過ごしてしまいます。ですので、いくつか試して眠れなくても「今回の方法は合わなかったな」程度に、深く考えすぎないことが大切だと私は思います。
ご自身に合う睡眠方法を見つけて頂けたら幸いです。筆者自身、過労→睡眠不足から身体を壊した経験があるため、健康に大きな影響のある睡眠に関する情報は積極的にお伝えしていきたいです。
参考資料:
▼良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと
https://e-kennet.mhlw.go.jp/wp/wp-content/themes/targis_mhlw/pdf/leaf-sleep_a5.pdf?1738108800119
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。今後も減塩や健康管理について役立つ内容を共有していきます。